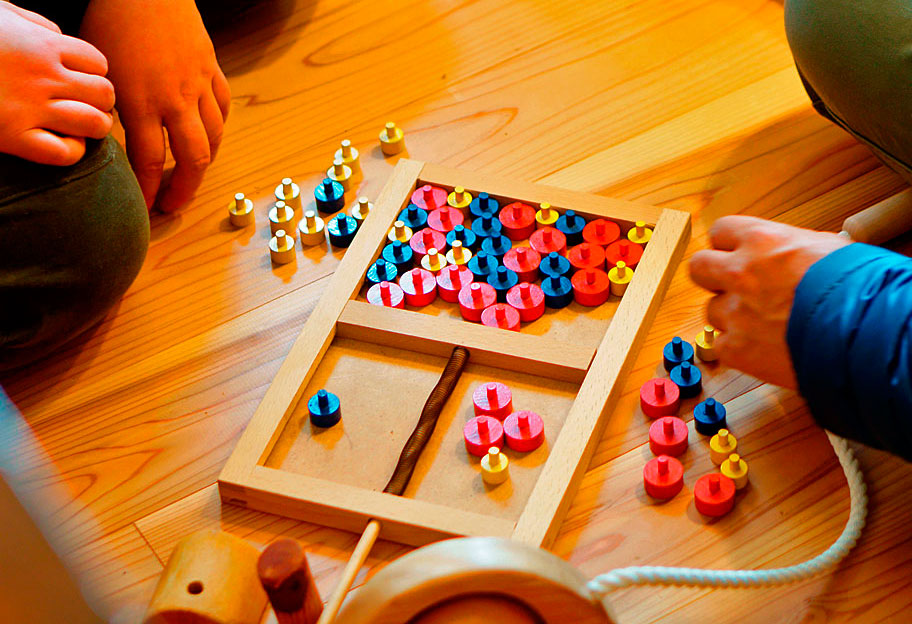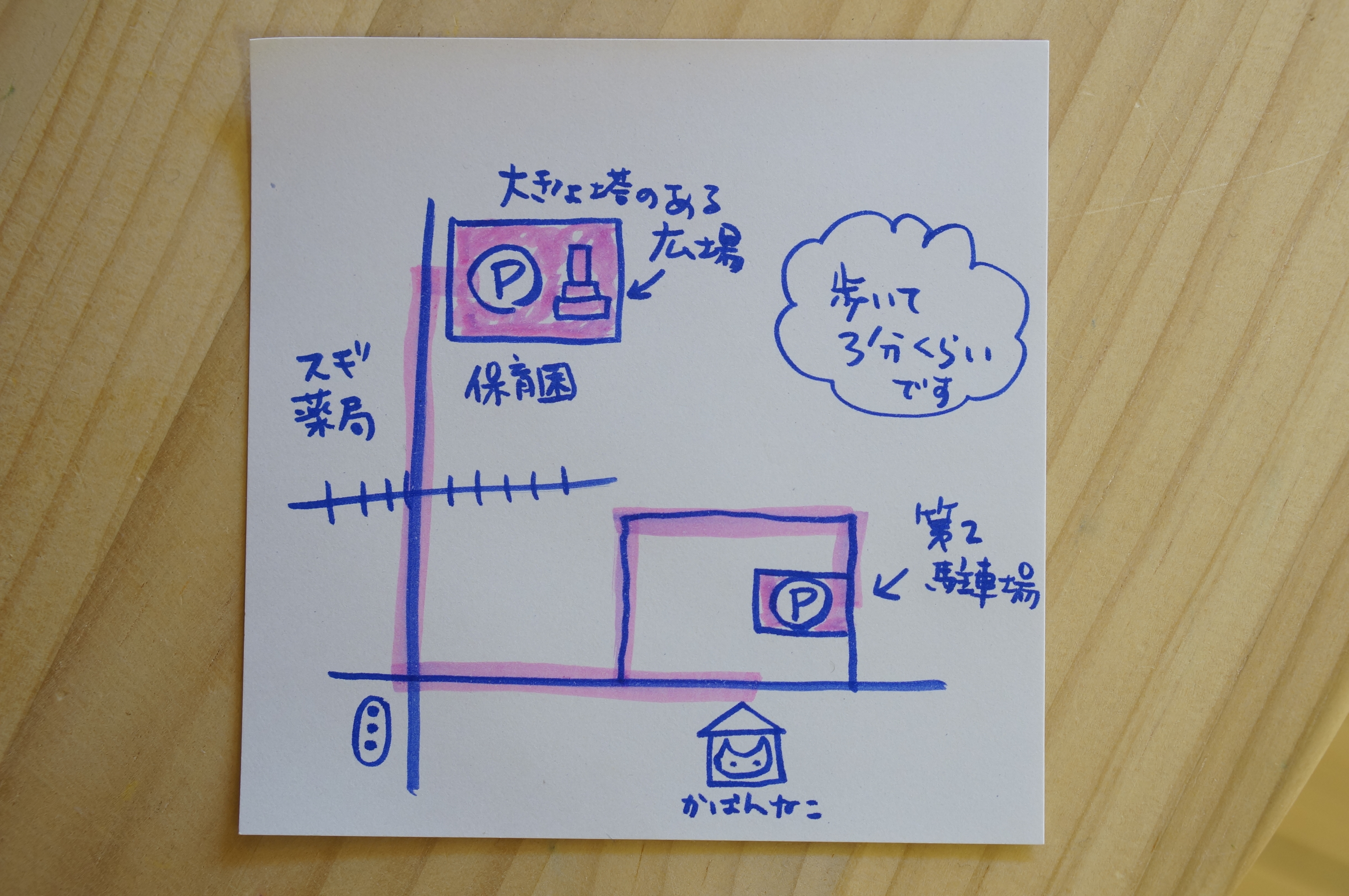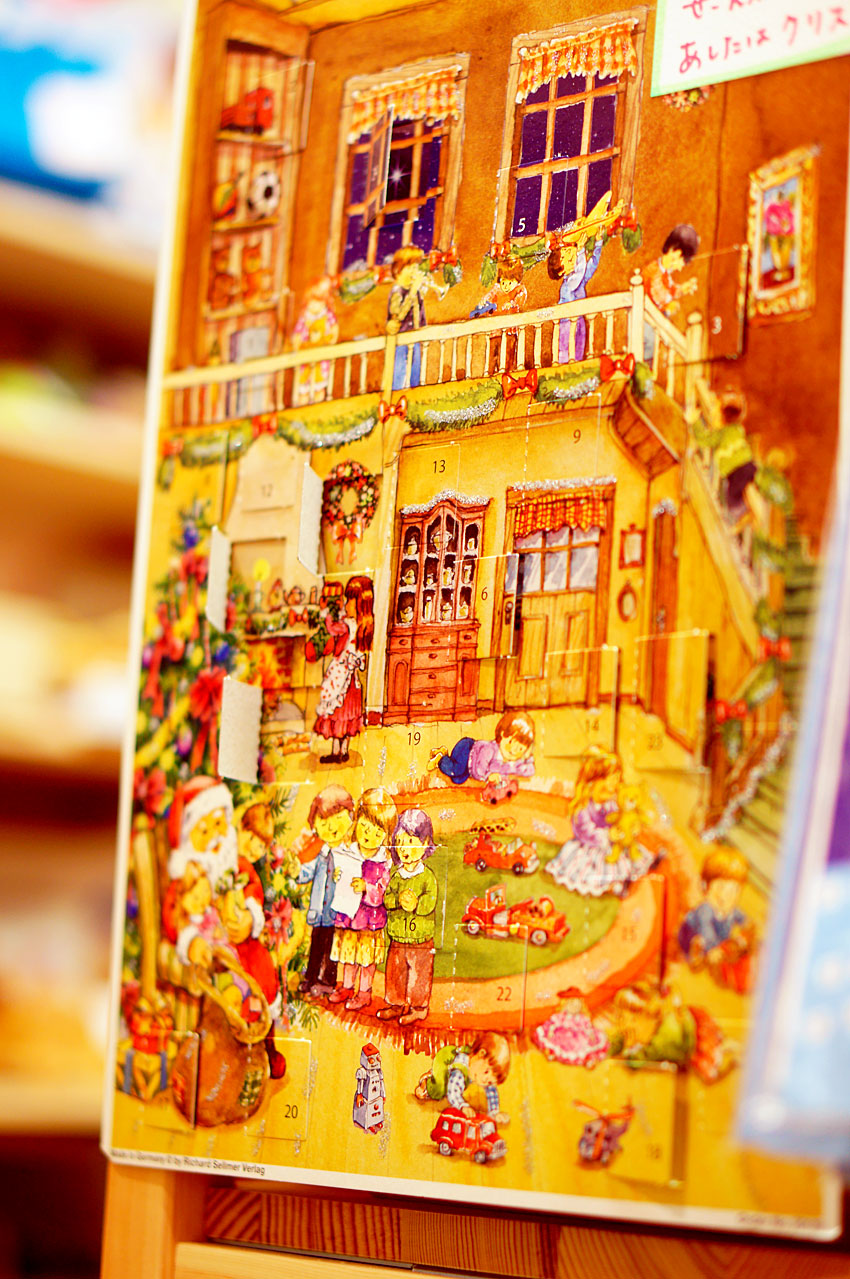おもちゃ箱、使っていますか?
おもちゃは、お店にならんでいるみたいに置いてあげると、持ってきやすいし、片付けやすいですよ。
なんでもかんでもおもちゃ箱では、整理する力もつきません。
いつも見えているから、「あれで遊ぼう」となるのです。
おもちゃ箱のなかは見えないし、いろんなものがごちゃまぜ。
子どもにとっては見えているものが全てで、
見えないものは、無いのと同じです。
(わたしたち大人も、食器棚の奥に押し込めてあったお皿を見つけてびっくりしたり)
子どもには、どんなおもちゃを与えたらいいのかな、
それにおとなはどんなふうに関わっていけばいいのかな、
子どもの育ちのために、どんなお手伝いができるんだろう。
かばんねこがよく聞かれることです。
でもその「成長のお手伝い」のなかには、おもちゃを通じてできる「生活習慣」もあるんですよ。
それは、おかたづけ。
おかたづけには、考えるちからが必要です。例えば、
同じものをさがす、
分ける、
順番にする、
もとに戻す、
先にやることと後にやることを判断して見通しをつける、
効率を考える…。
こうして出してみると、子どもに育てたいことがたくさん隠れています。
生活のなかで大事で、必要で、しっかりつけてあげたい力です。
(だから「お片付けしなさい!」と怖い顔になっちゃう)
わたしたちは、よく使うフライパンを、台所の使いやすい場所に置いておきますよね。
そして使ったら、かならず同じ場所に戻します。
どうしてでしょう?
それは、そうしないと、不便だから。
お片付け…整理整頓は、使いやすさのための工夫です。
それを、子どもの暮らしにも役立てられるはず^^
いつものおもちゃが、いつも決まった場所にあって、
使い終わったら、もとの場所にもどす。
使いやすい台所と同じように、子どもの場所をつくってあげる。
教え込み、やらせる。
そんな「しつけ」ではなくて、
おかたづけは、生活のなかで自然に「習慣」にしていくことができます。
子どもの日常である、
おもちゃを通じて。遊びを通じて。
…ということで、今日もお誘いします。
そんな「子どものあそびとまなびの講座」。
だって、ぜったいに役に立つし、おすすめだから!
お席は午前中がひとくみ、13時からの回は3くみ大丈夫です。
大人のかただけのご参加もあります。
お電話をいただいて、子どもの年齢とは別の回に参加されるかたも。
どの回に参加したらよいか迷われるかたは、遠慮なくお問い合わせくださいね^^

https://kabanneko.com/news/kouzamonotohito/